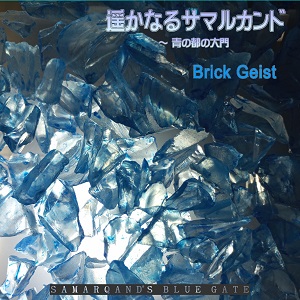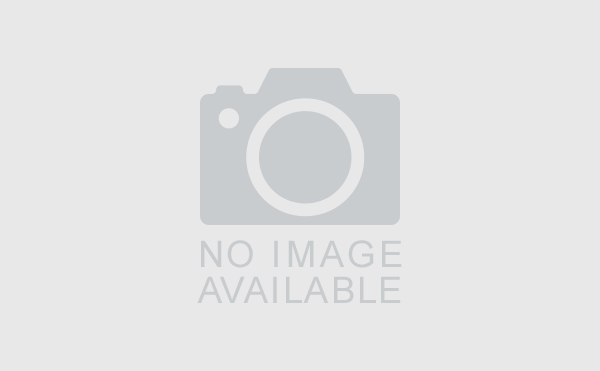グラフィックEQよもやま話
ヤマハの古い2chグラフィックEQを導入しており、以前も書いたがアナログマスタリングに使用。Youtubeを見てもパラメトリックEQの使用例ばかりだし、入れる前はどうなることかと思ったが、理論的には可能なはずなので、この場合は世間でやられてなくても理屈が勝った。
(といっても、もちろんマスタリング用のお高いパラメトリックEQのような音にはなりません。そんなに都合のいい話はない)😣
ただやっぱりアナログ色が出ていい感じになる、特にウチは70-80年代楽曲の音を理想としてるので、当時のようなやり方に近づけると、マスターが「同系統」の音になっていることがわかります。これは嬉しいですね。
EQを入れると少し位相がふわっとするんですね。これはアナログEQの特徴だそうで、音に立体感が出るといわれているようです。(確かにその通りだと思う、本来は有害なハズだけどね)
古いEQなので、さすがに少し歪成分も付加されますが、この場合はサチュレーション効果といえる。アバタもエクボ、みたいなもん。デジタルだと、生シンセも耳障りな高域成分がアラのように出ることがありますが、このあたりを見事に緩和してくれる。これはプラグインやデジタルマスタ処理では無理。
ただ、古いEQだとこうなるが、新しいEQではどうなるのか、という興味も当然あります。音の透明度はどこまで確保できるか、どんな系統の色が付くか、も。この辺りは当然メーカーや機種によっても違ってくるはず。
アウトボードは、超ハイファイや超クリア音質を目指さない限り(そっちはメジャーレーベルに任せた😉)、低コストでもなかなか面白い世界といえそうです。
うちのヤマハEQは、バイパス状態でも少し音質変わっています。いわゆるトゥルーパスでなく、回路を通っているからでしょう。
(まあ、といっても、イマドキ曲の音は音圧上げまくりドンシャリMAXで酷いものが多いから、それならプラグインで充分だったりね。アウトボードで微妙なフレーバー付けても意味がない。スマホに最適化された結果です。……まさか、だから最近のマスタリングスタジオってアウトボードが少ないのか?)