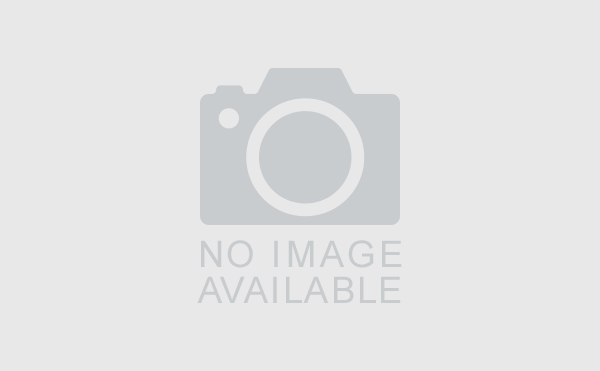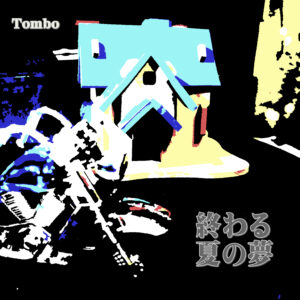ドビュッシーの名曲を解析した結果
クラシックの名曲で、ドビュッシーの「亜麻色の髪の乙女」というピアノ曲がありますが、この曲昔から好きなんですよ。基本そんなにクラシックは聞きませんが。
この度思うところがあって、まずはじっくり解析してみました。
著作権切れのパブリックドメインなので、有り難いことに楽譜やMIDIもフリーで配布されています。これをDAWに取り込んで作業します。楽譜は印刷しました。小品なのでわずか2ページ。
クラシックの譜面なので、当然コードネームのような堕落した功利主義の象徴(んなことないか😅)は書いてありません。だからDAWと譜面をにらめっこしながら、実際音を鳴らしてコードをつけていきました。ほんとはこれ、冗談でなく怒られるって聞いた。クラ業界はディグリーと展開形で解析していくのが作法らしい。まあ僕らは商業音楽の徒だから、そこは勘弁して頂くとして……。
3/4拍子、BPM66。ただし実際のピアニストの演奏を聴いても、インテンポできっかり弾く人は多くないようです。ぽつりぽつりと、ある意味つぶやくように演奏されがちです。(譜面にもフランス語で指示がある)
コードを付け終わって、ざっとストリングスの音で鳴らしてみましたが、もうなんというか驚愕です。まあとにかく耳が幸せ……。なんだこれ。名曲だからいってしまえばそれまでですが……。ドビュッシーの楽曲は音響的で響きが美しいのは確立した評価ですが、こんなに美しいコード進行だったとは。この曲自体、割と旋律的な曲なので、こうしてコード進行をしっかり聞くと耽美的ともいえる進行なのがわかります。
もちろんトライアドでなくテトラド(少なくとも自分はそう付けた)、オンコード連発、一時転調あり、ペンタトニックのユニゾンギミック(といったら怒られるか😆)ありで、まあお洒落なこと。
というか、気付いた。大体70年代以降のお洒落コード進行の元祖って、たぶんドビュッシーあたりなんですね。書かれたのは1908-12年頃なので、50年以上先行してました。当時は大変な驚きだったんじゃないか。これでテンションが入ってきたら、もうそのまんまですね。ストラヴィンスキーはもう同時期導入してたんだったか。
譜面を何度も見ても、無駄な音が一音もないし、まあ震えがきますよ。大作曲家の曲はこんなに凄いのかと認識を新たにした次第。さすがに世界中どの時代の人にも「良い」って言われる名曲です。
ちょっとまだ言い足りないことがあるので、また書きます。