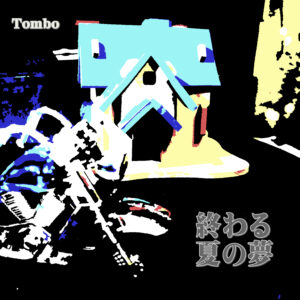ドビュッシーの名曲話続き
前回の続き。「亜麻色の髪の乙女」(La Fille aux Cheveux de Lin)、このピアノ曲はやはり、何から何まで計算され尽くされていて、例えば調はGbメジャー(変ト長調)で五線譜にフラットが6個付くわけですが、これを素直なGやFにして弾いてみると、雰囲気が全く変わってしまいます。元のほのかな官能性みたいなものが消えて、平たくいえばまあ台無し。Gbで音階の駆け上がり(下がり)があると、黒鍵が多いからふわっとして実にいい感じなんですね。(少なくともこの楽曲の中では)
だからもちろん調も熟考の上決められたものでしょう。むしろこれしかない、という感じ。
ここからが少し面白い話なんですが。どうやら調べてみると、この曲は元はドビュッシーが若い頃に書いた歌曲だったそうですね。女性オペラ歌手に書いたそうですが、どうもイケナイ恋だったらしく(→今なら文春砲😅)、演奏によっては時にエロチックにも聞こえるのは、そんな理由かもしれません(ただこの恋の件やや出所が怪しい)。公式には、スコットランドの草原で出会った少女のことを詠んだ仏詩人の詩、から着想された曲ということです。
あと、この曲は「前奏曲集」という24曲のピアノ曲からなる“シリーズ”の一曲ですが、この曲集、多くが元ネタがあったりするんですよ。詩やら他の芸術作品やら。これって何か思い出しませんか? ……そう、YOASOBIですね。😉 結構クラシックの曲は、詩などから採られたものも多くて、実はYOASOBI方式は新しいようで昔からあったんだな、と気付いた。これも元祖はクラシックでした。
譜面をよく見ると、全くの同音を左手と右手で同時に弾く箇所が3箇所くらいありますが(音価は違う)、最初は誤植かと思ったがもちろん合っていて、実際にそうやって弾くことを指定しているようです(単なる声部の都合ではないということ)。このあたり、弾き方によって響きが大きく変わってくるので、もうそれはドビュッシーからピアニストへの挑戦状と取れますね。これも啞然としました。
今から百年以上前に書かれた曲が全く古びていない、むしろ現代ポピュラー音楽の元祖だったというのは、自分にとっては大きな発見でした。