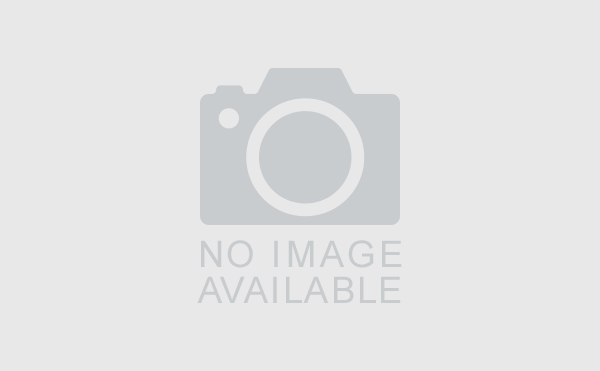グラフィックEQ(アウトボード)使用感
アナログシンセの音が真空管コンプ「PRO VLAII」を通すと歪み過ぎてしまう問題、なんと解決。
実はヤマハの2chグラフィックイコライザーを買っておいたんですが、試しに一緒に使ってみたら、これが驚きの効果。アナログシンセの歪み過ぎ感を見事に打ち消して、自然に馴染ませてくれました。全体的にもアナログフレーバーが付加され、真空管コンプのカラーをソフトにしてくれた感じ。
昔ならともかく、現代のマスタリングでは、皆様ご存知の通り、グラフィックEQ(以下GEQ)は使われず、パラメトリックEQ(以下PEQ)の方が使われます。アナログ感やPEQ独自のカラーで、色を付ける感じですね。
Youtubeを見てもGEQでマスタリングしている動画は見つからないし、商業マスタリングスタジオのサイトを見ても置いていない。どうだろうと思いつつも、理屈の上ではGEQでもアナログマスターを作れるはずなので、やってみたら、これが大当たり。
PEQは確かに魅力的な音になるが、まあ現実問題、お高いわけですよ。APIだSSLだというとすぐフラグシップシンセくらいの値段になる。
それに比べたらGEQは新品でも非常にリーズナブル。しかもオークションではもう詐欺みたいな値段で入手可。今回は少し色がつくことも期待しているわけだから、古めの機種の方が却って都合がいい。で、状態が良さそうなものを選んだのですが、ドンピシャでした。
ひとつだけヤバかったのは、EQのフェーダーを上げすぎると音源の位相が狂う、という点。中古故か、機種特有のものかは不明ですが、たぶん新品でも同じでしょう。リニアフェイズではないので、普通のEQプラグインと同じで位相が狂うことがある。(音が左右でふわふわ揺れます)
左右のEQカーブを慎重にあわせて、さらに+2dbを若干超えていた周波数ポイントを下げてみたら、位相ズレは消えました。元々マスタリングではEQの調整幅は+/-2db以下にするのが定石なので、これで運用できそう。
当然、トータルリコールは出来ないので、例によってEQのフェーダー位置をスマホで撮影しておく必要はあります。が、その不便を補って余りある効果がある。
いやはや、自分のようなアナログミックスを目指す人間には、今は結構良い時代といえそうです、意外にも。70-80年代の洋楽サウンドが理想なわけで、やはりその時代にやっていた方法に近づけていくと良い結果が出るようです。
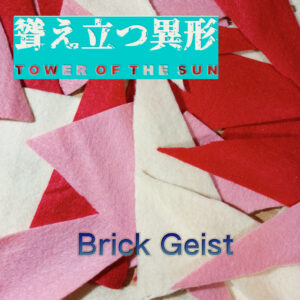 次回リリース曲はGEQ+VLAIIでフルアナログマスタリング
次回リリース曲はGEQ+VLAIIでフルアナログマスタリング